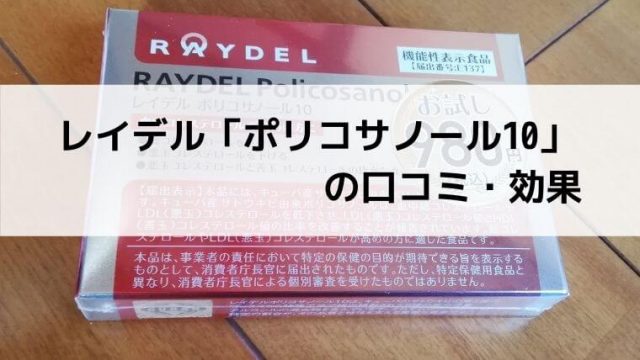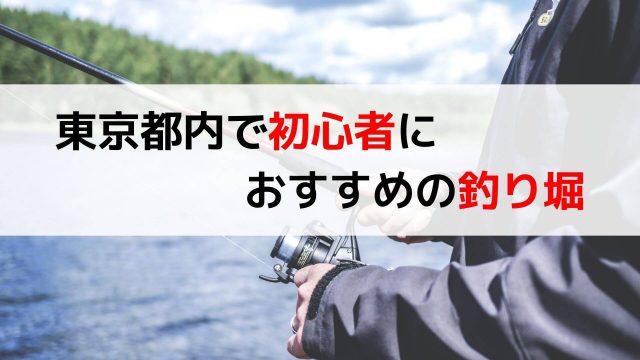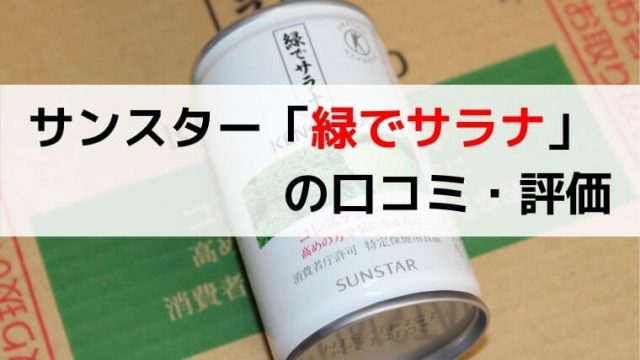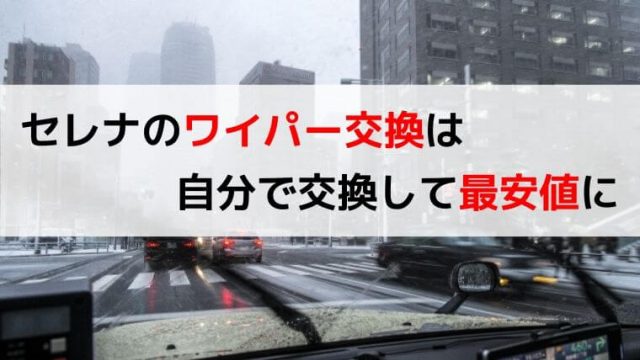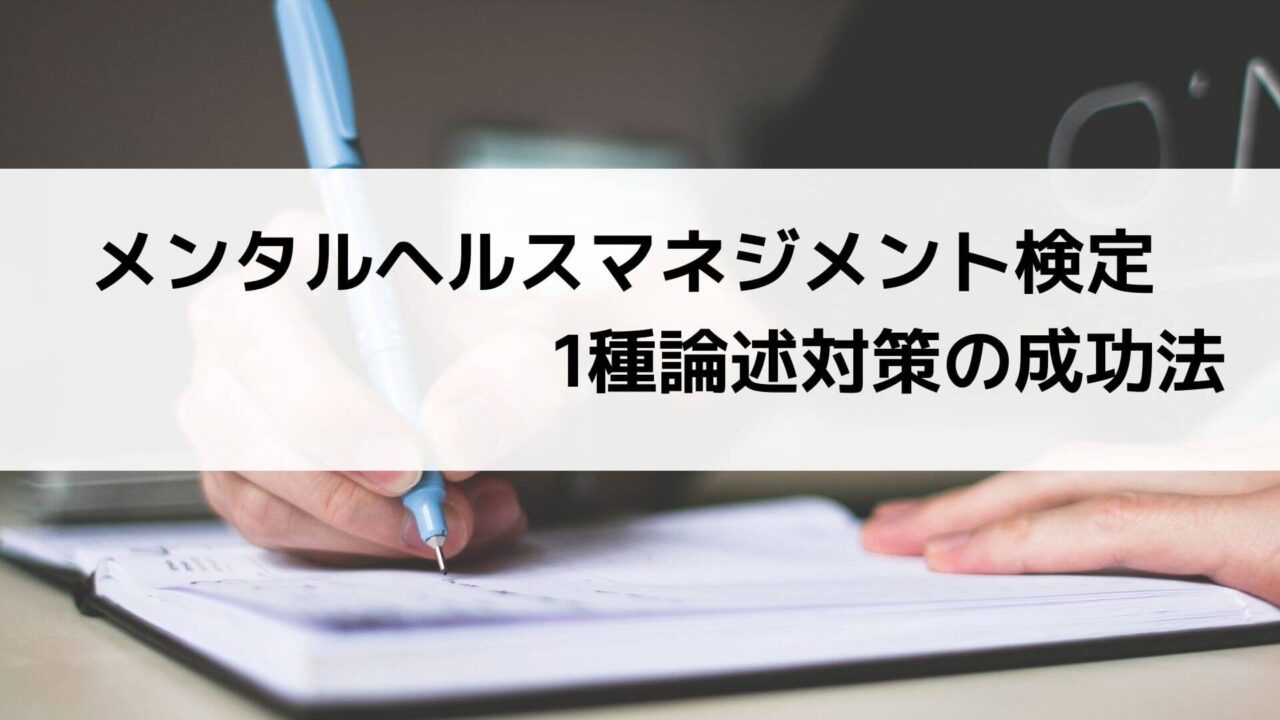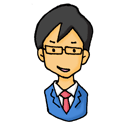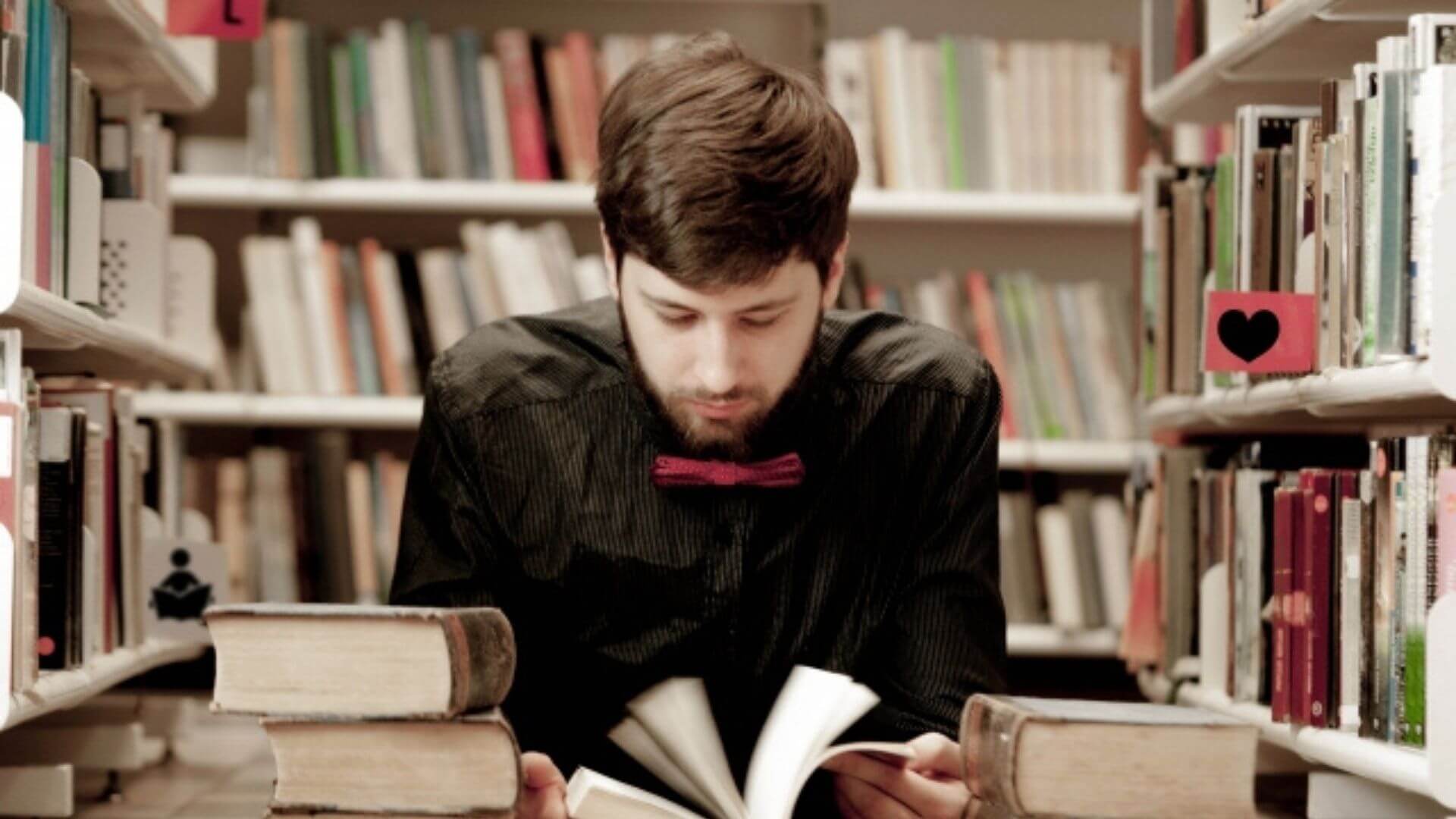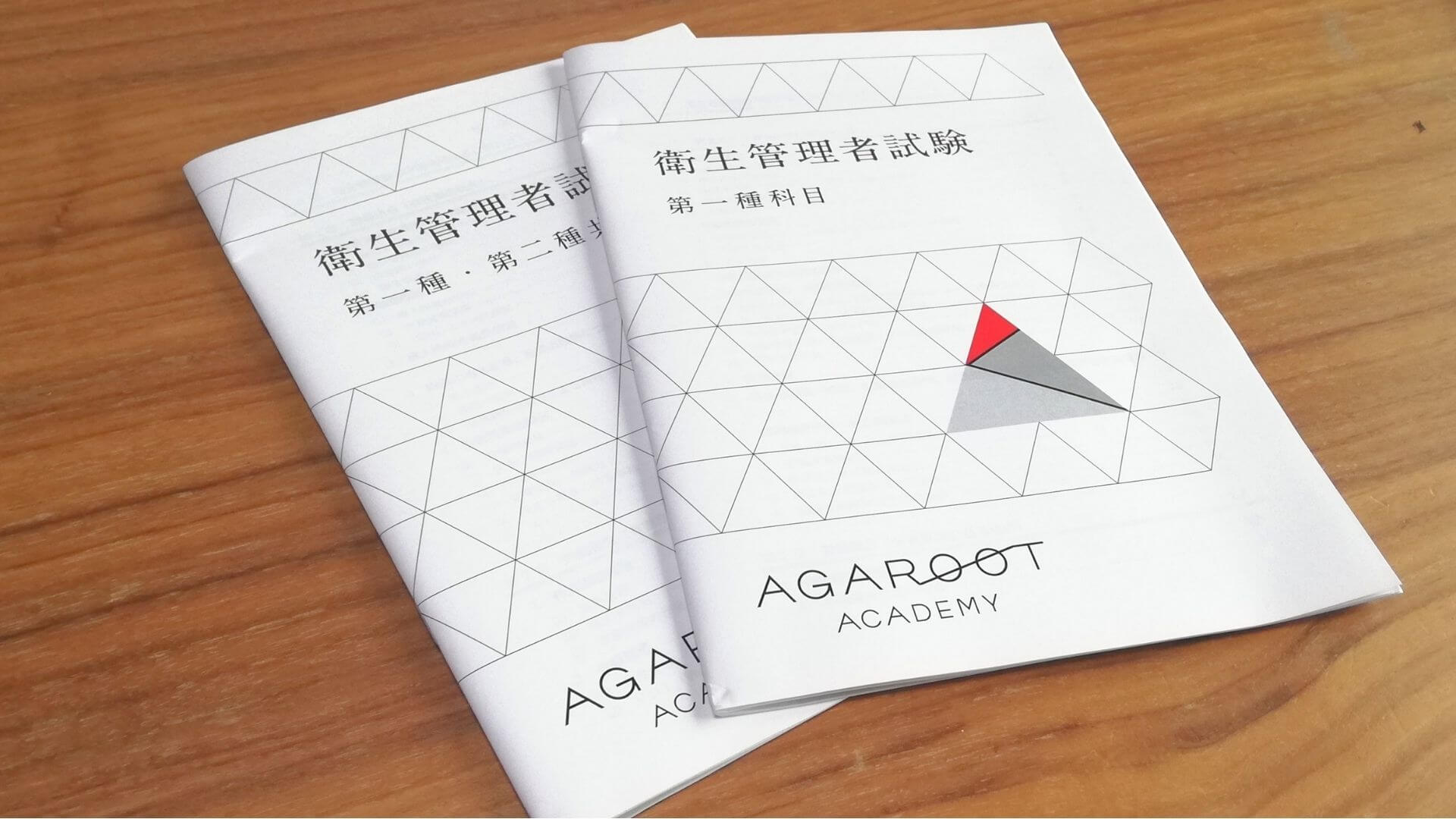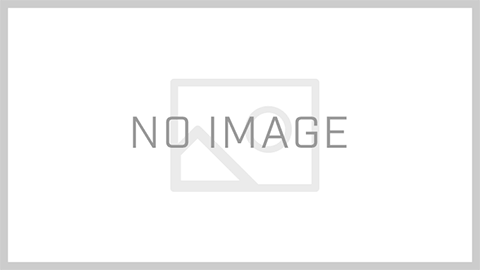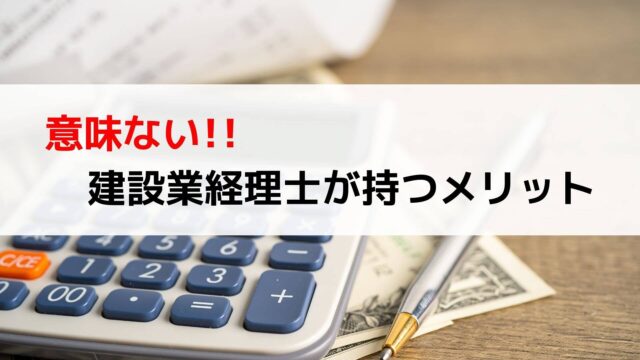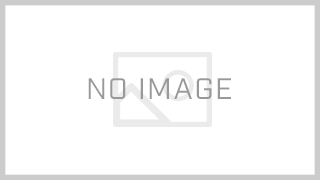メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策に関する情報を総合的に解説いたします。
メンタルヘルスマネジメント検定1種は、メンタルヘルスに関する深い知識と実践的な内容を含む難易度の高い試験となっています。またメンタルヘルスマネジメント検定1種の論述問題は、暗記だけでは通用しなく多角的な視点と応用が必要で、論述対策を講じておかないと試験合格が難しいです。
目次
メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策
メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策は、公式テキストの徹底的な読み込みと理解となります。
メンタルヘルスマネジメント検定1種を主催する大阪商工会議所が発行している『公式テキスト』は、試験範囲の基盤となることから、全464ページの内容を徹底的に読み込み理解することが論述対策の一番の要点となります。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策としては、合わせて下記の3つを実践することも大切です。
- 過去問演習と解答例の分析
- 論述作成の練習
- 最新情報のキャッチアップ
メンタルヘルスマネジメント検定1種は、過去問の公開していなく、受験者には無断転載を禁止しているので、メンタルヘルスマネジメント検定1種の試験内容を知る術は、中央経済の『メンタルヘルス・マネジメント(R)検定試験1種マスターコース過去問題集』を購入するしか手立てがありません。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の直近6回分の選択肢問題と、直近4回分の論述問題が収録されています。
毎年8月頃に最新版が発行されているので、昔の論述問題が知りたければ、2020年度版、2016年度版を購入することで昔の論述問題を知ることが出来ます。
論述対策は過去問から論述作成の練習実施!
論述対策は、過去の論述問題を自分なりに解答する練習を何度も実施してコツを掴むことと、論述問題に対する閃きを養いましょう。
- 自分なりの考えを論述形式でまとめる練習
- 論理的で説得力のある文書作成の練習
- 時間内に論述問題を解く練習
日本能率協会マネジメントセンターの『メンタルヘルス・マネジメント®検定試験1種(マスターコース)重要ポイント』は、論述対策としてキーワード集が掲載されているのでおすすめです。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の公式テキストの要約テキストとして、初めて勉強する時にどんなことが書かれているのかの概要を知る上で、役に立つテキストとなっています。
最新のメンタルヘルス情報のキャッチアップ
公式テキストは、2021年7月に発行されていて統計データが古い!最新のメンタルヘルスの統計データを確認しておきましょう。
《2025年7月現在のメンタルヘルス統計データ》
その他、公式テキスト内で紹介されていても、最新のメンタルヘルス情報でない場合もありますので、最新情報をしっかりとキャッチアップしていくことが論述対策になります。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の独学勉強法
メンタルヘルスマネジメント検定1種の独学は「選択肢問題対策」と「論述対策」の2軸で勉強するのが効率的です。
論述対策で、公式テキストの徹底的な読み込みと理解が出来ていれば、選択肢問題対策は簡単です!
中央経済の『メンタルヘルス・マネジメント(R)検定試験1種マスターコース過去問題集』を3回やり正答率90%以上になります。
過去問の記録表として「メンタルヘルスマネジメント検定1種 過去問記録表」を作成したのでダウンロードして使って下さい。
独学に適したテキストや過去問集!
メンタルヘルスマネジメント検定1種の独学に必要なテキスト・問題集を紹介!
メンタルヘルスマネジメント検定1種を主催する大阪商工会議所が発行している『公式テキスト』!これが試験問題のベースなので、絶対に必要なテキストとなります。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の唯一の過去問集!中央経済の『メンタルヘルス・マネジメント(R)検定試験1種マスターコース過去問題集』を購入するしか過去問を知る術がない。
メンタルヘルスマネジメント検定1種は、毎年1,500人前後と受験者が少ない状況です。そんな中、テキストを作成しても販売数は延びないので、根本的にテキストを選べるほど種類が無いのが実情です!
メンタルヘルスマネジメント検定1種の独学ツール
メンタルヘルスマネジメント検定1種合格者による、勉強のノウハウを販売している個人がいます。
合格時に自身で作成した勉強ツールなので、合格実績のある有用な勉強ツールとなりますが、あくまでも教育の素人が作成しているので抜けなどがある可能性はあります。
| 販売先 | 販売者 | 商品名 |
|---|---|---|
| メルカリ | スタープラチナ&ザ・ワールド | メンタルヘルスマネジメント検定1種(マスターコース) 論述対策問題集 |
| note | ひつじさん | メンタルヘルスマネジメント検定一種いきなり受検、独学一発合格を実現した論述対策 |
| note | こかさん | メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 論述対策ポイントまとめ【第1章】 |
ちなみに私は、『メンタルヘルスマネジメント検定一種いきなり受検、独学一発合格を実現した論述対策』を購入して勉強をしました。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の通信講座の特徴
メンタルヘルスマネジメント検定1種の通信講座は、日本マンパワーしか、存在しないようです。
- 論述対策としてオリジナルの「論述式問題攻略BOOK」がセット
- 論述対策として論述課題を提出すれば、講師が添削指導する
- 過去3年分の論述問題と模範解答が収録されている
- 通信講座費用には、公式テキスト代も含まれる
メンタルヘルスマネジメント検定1種の合格のカギである論述対策に力を入れている通信講座ということが分かります。
メンタルヘルスマネジメント検定2種なら「スタディング」「ユーキャン」「LEC
」などの大手も通信講座を出していますが、メンタルヘルスマネジメント検定1種となると受験者数が少なく採算が合わないのでしょうね。
自分に合った通信講座の選び方とは
通信講座を選ぶ際は、通信講座の学習スタイルと、あなたの学習スタイルが合っているかが重要です。
教材の質や講師陣の専門性が高く、合格実績も多数ある通信講座でも、あなたの学習スタイルと合っていなければ、その通信講座で学習しても合格することは難しいでしょう。
- 学習効率の悪化
- 自己管理の難しさ
- 疑問点の解消の遅れ
- モチベーションの低下と挫折
- 試験本番での実力発揮の難しさ
通信講座は、自身のペースで学習を進められるという大きなメリットがある反面、自己管理能力が問われることとなります。
メンタルヘルスマネジメント検定1種合格への近道
メンタルヘルスマネジメント検定1種合格者の体験談から学びましょう。合格の秘訣と共に、失敗からの重要な教訓も理解することが大切です。
メンタルヘルスマネジメント検定1種合格者の体験談
がメンタルヘルスマネジメント検定1種合格者の体験談&勉強方法を紹介されているので、勉強方法などの情報を収集していきましょう。
メンタルヘルスマネジメント検定1種攻略法
メンタルヘルスマネジメント検定1種合格者の体験談を読むと、論述対策が重要なのが分かります。
ポイント1:頻出項目・法改正項目などを中心に勉強
ポイント2:実際に手を動かして書いてみる
しかし精神科医の井上智介産業医のブログ記事にも書かれていましたが「論述試験は、運の要素が強い!」
論述問題は、全464ページの公式テキストの中からピンポイントで出題されます。
「イネイブラー」とは
公式テキストの中で「イネイブラー」のことが書かれているのは、●●ページの「」と言う項目で、●行だけです。
そのピンポイントの●行の内容を、論述問題の回答に合うようにアレンジして深堀していかないといけないのですから、公式テキスト464ページ全てに対応することは、ほぼ無理だと言って良いでしょう。
メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策について【まとめ】
メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策について紹介してきました!
メンタルヘルスマネジメント検定1種の論述対策について紹介していますが、メンタルヘルスマネジメント検定1種には「選択肢問題」もあり対策していかないと、メンタルヘルスマネジメント検定1種合格はできません。
このブログ記事が、あなたのメンタルヘルスマネジメント検定1種合格の一助となれば幸いです。
これまでの努力が実を結び、見事合格を勝ち取れるよう心から応援しています!